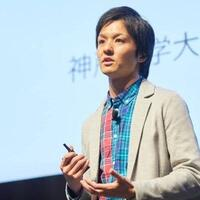経営学は企業や組織のあり方、その中で活動する個人の行動や組織との関係など、「現場」を対象とする学問だ。
服部泰宏准教授は、「現場の役に立つ研究」を追求し、多くの企業が課題を抱えている人材採用を分析・理論化する「採用学」のパイオニアとして、注目されている。現場重視の姿勢は、コロナ禍で影響を受けている企業や個人の実態研究にもいち早く結び付いた。社会が直面する課題に果敢に取り組む服部准教授に、研究姿勢、研究手法を語ってもらった。

企業の採用活動を分析、理論化する「採用学」を確立されました。この分野の研究に取り組まれたきっかけは何だったのでしょうか。
服部准教授:
研究者はどうしても自分の興味・関心に従って研究活動を進めることになりがちです。しかし、経営学は企業などの「現場」を対象にする学問であり、例えば2012年に訪れた米国の学会では、著名な研究者が企業の実務家と対話して、「企業経営にどう役立つ研究を行うか」を考えていました。彼らは同時に、どうして研究者の議論が「机上の空論」に陥りがちになるのか、と自己批判的な姿勢で研究活動を考えていて、これは私たちが見習うべき重要な姿勢だと感じました。組織と人の関係を考察した博士論文を単著として発刊して研究に一区切りついた2012年ごろ、次の研究テーマを探す際に、「現場の人に話を聞いてみよう」と考え、様々な企業の方と対話しました。すると「良い人材を採用するのが大変になっている」という悩みを話してくれる人が多かったのです。日本では採用関連の研究をしている経営学者はほとんどいなかったので、現場の役に立つ分野として採用の研究を始めました。

具体的にはどのような手法で研究を進めたのですか。
服部准教授:
現場(企業)に通って話を聞くことと、データの収集・分析の二本柱で研究を進めています。データはアンケート調査と人事データの2種類を扱い、立体的に分析します。例えば、人事データでは採用時のSPI(適性検査)や面接での評価と、入社3年後のパフォーマンスとの相関関係などを分析します。SPIではある特性が「優秀さ」につながる、と考えるわけですが、優秀さをどのようにとらえているのかを企業の人事担当者に聞きに行きます。データとインタビューを組み合わせて、複数の観点から、企業の採用活動を評価・分析しています。
先生の著書『採用学』では、多くの企業が採用時に重視する面接が、入社後の優秀さにほとんど結びついていないと指摘されています。
服部准教授:
面接には、面接者が自由に質問する「非構造化面接」と、あらかじめ質問項目・内容を決めておいて全員に同じ質問をする「構造化面接」があります。このうち、日本企業の多くが前者を行っていると言われているのですが、その結果、どの程度、入社後の「優秀さ」を予測できているだろうかと疑問を持ちました。いくつかの企業から人事データをいただいて分析してみると、残念なことに、多くの日本企業において、面接時の評定と採用後の優秀さ(例えば、営業担当者のパフォーマンス)との間に相関関係がありませんでした。10社以上の企業で同じ分析を行いましたが、SPIなど一部の指標にはパフォーマンスとの多少の相関関係が確認されたものの、3年前(採用時)の面接スコアと実際の人事評価との間の相関関係はほとんどみられなかったのです。
ただ面白いのは、米国での研究においては、面接と採用後のパフォーマンスの相関関係は、少なくとも構造化面接を行っている場合には、ある程度高い値になる、というデータが示されているということです。これには米国と日本の人材採用や人事制度の違いが関わっているのだと思います。米国は特定の職種・仕事を担当する人材を採用するジョブ型採用なので、採用面接も構造化しやすい。一方、日本企業はどの仕事を担当させるか決めずに採用する、社員になることを約束するだけのメンバーシップ採用なので、構造化しにくいのです。入社面接では「この人は感じが良い」とか「社風にあっている」などの一般的な印象で評価され、仕事を遂行する能力を見ているわけではないのです。したがってそこで「100点」がついたとしても、それは必ずしも、業務遂行能力が「100点」であるということにはならないのです。
そのような日本企業の採用方法が変化し始めていることを明らかにされました。
服部准教授:
2015~16年ごろから、採用方法を多様化する企業が出始めました。『採用学』や『日本企業の採用革新』(中央経済社)でも紹介した新潟県の三幸製菓のように、採用の入り口を複数化して人材の多様性を確保しようという動きが目立っています。採用の入り口・ルートを、<社員による紹介>、<インターンシップ>、<地頭(じあたま)の良さをみるテスト>など複数にしたり、通常の真面目な採用だけでなく遊びの要素を取り入れたイベントで入社希望者の本音を深掘りするなど、他社とは違う採用方法で差別化を図り、採用の同質性を破る試みが出ています。
売り手市場といわれた人手不足が背景にあり、新興のベンチャー企業や多様な才能の人材が必要なヤフー、サイバーエージェントなどのメガ・ベンチャーが、新しい採用方法にチャレンジし始めました。人手不足・採用難に加え、「これまでと同じような人材で成長できるのか」という問題意識をベンチャー企業などが感じ始めたという背景があったと思います。
創造性に富んだ人材、突飛な発想・天才的なひらめきのある人がいないと成長できないという意味で、優秀さの条件が変わってきました。多くの入社希望者を集める大手企業にも波及し、何らかの形で採用方法を多様化したり、採用・人事データの分析を自前で行うことが普通になって来ています。
「採用学」だけでなく、新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年には、コロナが企業や個人に及ぼした影響を実証的に研究されています。
服部准教授:
コロナ感染拡大前に、組織学会の研究者30人強で、企業の現場で起こっている問題を診断するアンケート調査を計画していました。(自らの仕事も遂行しながら部下の指導・管理も行う)プレーイング・マネジャーの疲弊や、現場の意思決定の自由度と創造性の関係などのテーマを考えていましたが、新型コロナ感染症の影響を受けている企業の現場に負担・迷惑をかけると考え、コロナの影響にフォーカスした調査に切り替えました。リモートワークの実態や資金難、現場のミス多発などの影響について、三百数十社を対象にアンケート調査を4月にお願いしました。コロナの影響を経営者や人事部門が打ち出す施策のレベルで検討する、いわばマクロレベルの調査です。加えて、私が所属しているもう1つの研究グループでは、コロナの影響を個人、つまりミクロレベルで捉えるということも行っています。企業・組織という「マクロ」と、個人レベルの「ミクロ」で、現場でのミス多発や新製品開発の停滞、失業や収入の激減、人間関係の希薄化などの悪影響が確認された一方で、業績が向上する企業もあるなど、かなり「個体差」があることがわかりました。
その違いは何によるのでしょうか。
服部准教授:
注目しているのは、危機の際に柔軟に対応する力=「レジリエンス」です。アンケート調査ではコロナ危機前のことも質問しているのですが、従前からレジリエンスを備えていた企業が危機を乗り越えていました。レジリエンスは、ある種の“無駄”を持っておくことがカギになっています。例えば、従業員の家族の状況、仕事の癖など、通常では必要ない情報を把握していることが、意味を持っていました。在宅勤務をしている従業員が、子どもを保育所に迎えに行く時刻を避けて仕事の指示をするとか、きめ細かい配慮をできることが大切になっているのです。また、会社への愛着を持っている人の方が、困難に負けずに頑張って働いていることも明らかになっていて、平時では無駄とされるような情報や企業と従業員の密接な関係が活用され、レジリエンスにつながっていることが見えてきました。企業は効率性追求だけでなく、レジリエンスを用意するために人間関係の冗長性などが必要であることを提言できました。マクロ、ミクロの二つの調査研究を書籍として出版する予定です。
今後の研究の方向性を教えてください。
服部准教授:
2020年9月に学術書『組織行動論の考え方・使い方』(有斐閣)を出版しました。現場に役立つ研究をするために、研究者は何をすべきかを考えた本です。それは、①良質のエビデンス、知識、論理を現場の人が理解しやすい形で届けることと、②現場との共同研究を活性化し、現場に新しい気付きを提供していく——ということです。現場の課題解決を共に考えていく中で新しい知識を得る、データをポンと渡すのではなく、付加情報を添えて現場に役立つように還元する、そういう研究を徹底的に考えて行きたいと思います。
略歴
| 2004年3月 | 関西学院大学経済学部 卒業 |
| 2004年4月 | 神戸大学大学院経営学研究科博士課程前期課程 入学 |
| 2006年3月 | 神戸大学大学院経営学研究科博士課程前期課程 修了 |
| 2006年4月 | 神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程 進学 |
| 2009年3月 | 神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程 修了 |
| 2009年3月 | 博士(経営学)神戸大学大学院経営学研究科 |
| 2009年5月~2011年3月 | 滋賀大学経済学部 専任講師 |
| 2011年4月~2013年3月 | 滋賀大学経済学部 准教授 |
| 2013年4月~2018年3月 | 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 准教授 |
| 2018年4月 | 神戸大学大学院経営学研究科准教授 |