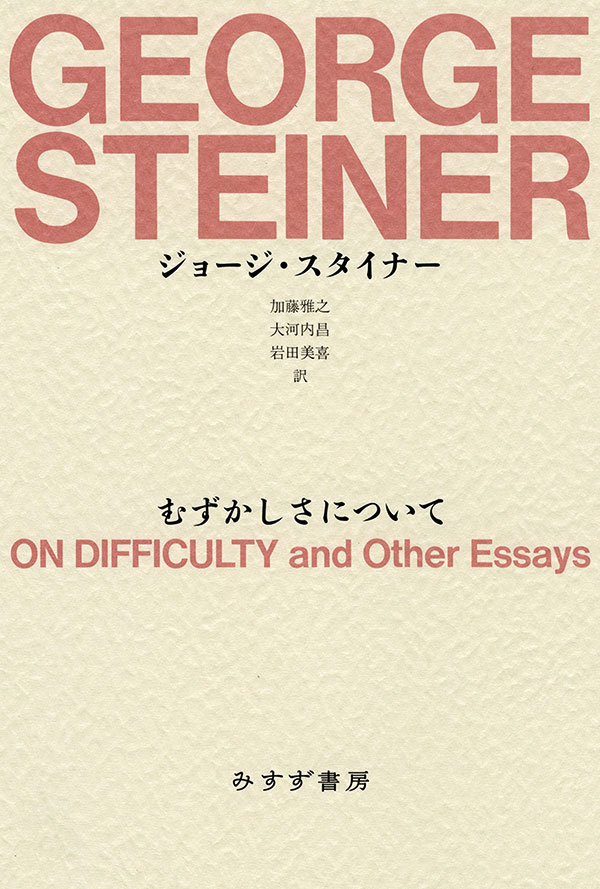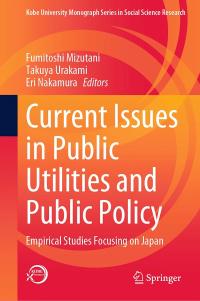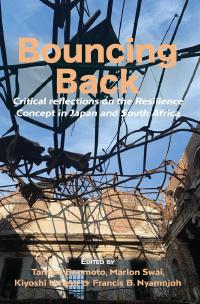本書はGeorge Steiner, On Difficulty and Other Essays, Oxford University Press, 1978の翻訳である。あらためて述べるまでもなく、著者スタイナーは英米文学批評の枠組を越えた、グローバルで領域横断的な批評・創作活動を半世紀以上にわたり展開している、紅白歌合戦の最多出場記録をほこる演歌の大御所のような(こぶしまわしに特徴のある歌い手のようにわれわれはスタイナーのいたるところにスタイナー節を聞く—もちろんこれは褒めているのである)研究者である。そして今でも旺盛な講演や執筆活動を続けている。
文学書や人文書が読まれなくなって久しいという。紙の本すら世の中から消えつつあるというのが実感である中、スタイナーとは縁が深い由良君美が「反能率的読書法」(『みみずく偏書記』)の中で「そもそも人文系の学問を、知識を蓄えるためにするのは邪道である。いかに多く学び多く忘れるかが正道である。逆説的に言えば、わたしは沢山忘れるためにたくさん読む。…読みに読み、忘れに忘れて、やがてそれが意識下に溜り、血を生む腐葉土となり」と吐露していたことが懐かしい。スタイナーはもっと直截だ。(From The Paris Review, 1994)
INTERVIEWER Aside from reading and writing and music, what are your other passions?
STEINER read and read and read.
一番最初に読み聞かせてもらった絵本、初めて自分で文字を拾いつつ読んだ童話、小遣いをためて買った文庫本、辞書を引き引き3ヶ月かけて通読したAgatha ChristieのThe Murder on the Links、ページの隅が折れ、ビスケットの粉がついてよれよれになった辞書…、本の思い出は手触りと匂いの身体的感覚とともにしまいこまれている。が、本書最後のエラスムスがぬかるんだ道に落ちている本の一部を見つけて狂喜したという一節は、電子図書館、電子書籍が一般的になった現在、より一層痛切に響く。しかし、「それはそれでまったく悪いというわけでもない」とスタイナーは結ぶ。楽観論的悲観論者の面目躍如といったところか。
本書の収録論文は以下、目次の8編。
国際コミュニケーションセンター・教授 加藤雅之
目次
- I テクストとコンテクスト(1976)
- II むずかしさについて(1978)
- III 言語と精神分析に関する覚え書き(1976)
- IV 言説の流通(1978)
- V エロスと用語法(1975)
- VI ウォーフ、チョムスキーと文学研究者(1974)
- VII ダンテはいま——永遠の相における噂話(1976)
- VIII 書物の後には?(1972)