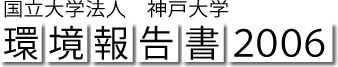環境に関する教育・研究と地域貢献
環境に関する研究
1. ごみじゃぱん (gomi-jp) について
経済学研究科 石川雅紀
環境関係の教育・研究活動を紹介することになりました。スペースも限られているので、 最近始めた活動で、本人が最も面白いと思っている例を紹介します。NPO法人ごみじゃぱん (通称 gomi-jp) を設立しました。
gomi-jp の目指すところは、維持可能な社会を目指して、ごみを削減することです。 活動の特徴は、産官学民の連携で無理せずごみが減らせる仕組みを作ることです。このために、 丁寧なインセンティブ設計とコミュニケーション、個別の問題解決が核となります。 社会デザインという言葉が適当かもしれません。
これまでは、社会の基本的なルールである法律や基盤となる制度は、 専門家の知識・経験に基づく判断を参考にして「お上」としての行政が実質的には決めてきました。 日本において「市民」は、自立し当事者意識を持って発言すると言うよりは、「お上」に協力を要請される対象でした。 一方で「市民」や民間企業は自分たちで解決できない問題に直面すると「お上」に頼る (裁定を期待する) 傾向がありました。 このシステムは、日本のように価値観が比較的均一化している社会において、 個別の問題解決に対してはこれまで比較的機能してきました (自立した市民による自治という根本的な問題は別ですが)。 私は情けないと思います。
しかし、現在我々が直面しているような維持可能な社会への移行というような多様な解があり得るような問題に対しては、 「お上」も「市民」もとまどうばかりです。維持可能な社会への移行は、与えられた条件の下で唯一の解があるような問題、例えば、 入学試験の問題のような問題ではなく、むしろ、どの解を選ぶかという選択の問題なのです。 このような問題に対して専門家ができる貢献は、選択とその結果の可能な範囲での客観的な予測と予測の限界の明示です。 「市民」や民間企業は正解のない問題で社会的な選択を行うことに慣れなければなりません。しかも選択の結果の予測は大変不確かです。 これは大変難しい問題です。暗闇の中を維持可能性という出口を求めて一歩一歩歩くようなものです。
非常に難しい問題に直面したときには具体的な例題に取り組んでみることが役にたつことがあります。 私にとって gomi-jp はこのような意味があります。gomi-jp には運動、社会実験、研究そして教育という意味があります。運動とは、 情報提供、丁寧なインセンティブ設計と個別の問題解決で実際に企業、行政、市民にとってウィンウィン関係で問題を解決できることを示すことによって、 より大きな流れを作る意味です。社会実験とは、これまで行われてこなかった規模のごみ削減社会実験によって社会デザインの重要なデータを得ることです。 研究は、これまで取り扱われてこなかった実際の生活者の行動や企業の行動を分析し社会実験で得られた知見を普遍化することです。 教育は最も重要な側面かもしれません。実は今年度の石川ゼミ (来年度もそうですが) は gomi-jp に参加する人を優先しました。 教科書の無い問題に取り組んで、自立した大人になってほしいのです。もちろん4年生になれば卒業研究として研究として成立するテーマを見つけて取り組んでもらいますが、 自立したどこに出しても恥ずかしくない学生になっているはずですから、オリジナルなテーマを見つけてくれると思っています。