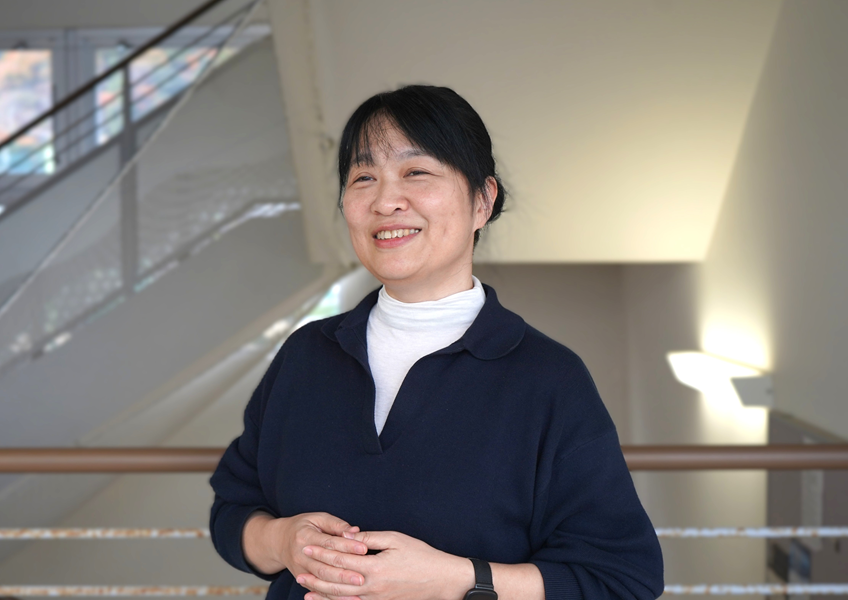睡眠の問題に悩む人は多い。個人の健康や生活だけでなく、社会全体の動きとも深く関係しているテーマだ。その睡眠を心理学の分野から研究し、地域や学校での知識普及にも取り組んでいるのが、人間発達環境学研究科の古谷真樹准教授。人間のウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に良好な状態)と睡眠の関係、正しい知識を普及するための「睡眠教育」の現状などについて聞いた。
ストレスと睡眠の関係を研究
専門は睡眠心理学ですね。そもそも、睡眠に関する研究にはどのような分野があるのでしょうか。
古谷准教授:
「睡眠学」の研究が広がり始めたのは1960年代ごろです。1950年代、米国の研究者が人間のレム睡眠(脳の活動水準が覚醒に近い睡眠)を発見し、研究が大きく発展していきました。1970年代には「日本睡眠学会」が誕生し、特にここ20年ほどは、幅広い分野の研究者が関わるようになってきました。
睡眠研究は、大きく分けて三つの分野があります。睡眠障害の原因解明や治療など医学的見地からの「睡眠医学」、睡眠の役割やメカニズムを研究する「睡眠科学」、社会生活上の問題と結び付けて研究する「睡眠社会学」です。
私が専門としている「睡眠心理学」は、睡眠科学と睡眠社会学を横断した分野です。研究している主なテーマはストレスと睡眠の関係で、大学院時代から取り組んでいます。日中のストレスが夜の睡眠に及ぼす影響や、日常的なストレスと睡眠の関係などを調べています。
研究で見えてきたことや現在の具体的な研究内容を教えてください。
古谷准教授:
ストレスと睡眠の関係を研究する中で、神戸大学に着任した当初は子どもたちのストレスに焦点を当てていました。学校での集団生活、受験、人間関係の悩みなど、子どもにはさまざまなストレスがありますよね。ただ、研究を進めるうち、保護者のほうの睡眠の問題が深刻だということが分かってきました。
保護者の多くは働き盛り世代のため、睡眠時間が短く不規則であることが多いです。それが子どもの睡眠習慣に影響する可能性があります。また、保護者が睡眠より勉強時間や習いごとを優先しがちだと、子どもの睡眠の問題も改善しにくくなります。
ですから、睡眠については親子で一緒に考えてもらうことが大切です。例えば、親子でそれぞれ睡眠日誌をつけ、一定期間後に記録を見せ合ってもらう方法があります。そうすると、互いの睡眠習慣について気づきがあり、改善に向けた話し合いができます。子どもが保護者の睡眠不足を心配していると分かって、保護者が生活を見直すきっかけになる場合もあります。
そのような親子の関係に注目した研究から発展し、現在、働き盛り世代のストレスと睡眠の関係について研究を進めています。20代から40代の人々を対象に、血圧や体温などの生理指標を記録してもらいながら、ストレスの早期発見方法を見出して不眠予防に貢献したいと思っています。
また、介護をしている働き盛り世代の生活について、ニュージーランドの研究者と共同研究を行っています。日中に働き、夜も十分に睡眠がとれない介護者の場合、どのような要因が疲労やうつ症状に影響するのかを調べています。日本もニュージーランドも、睡眠の満足度や低強度の運動習慣といった影響要因は大きく変わらないのですが、日本のほうがうつ症状を呈する人の割合が高くなっています。両国の違いを分析しながら、ストレスに対応する方法を提示していければと考えています。
睡眠ではなく、昼間の生活を変える
地域や学校で睡眠について話す機会も多いとのことですが、そのような「睡眠教育」の場で特に意識して伝えていることは何でしょうか。
古谷准教授:
「睡眠だけを考えるのではなく、昼間の生活を考える」ということです。質の良い睡眠をとるためには、日中に体をよく使い、人との関わりなどで脳を使い、食事をしっかりとり、湯船につかって入浴する、といった生活習慣が重要です。睡眠ばかりに焦点を当てて考えても、睡眠の問題は改善しません。
ただ、完璧を目指す必要はありません。日中に少しだけ運動してみる、といった小さなことから始めればよいと思います。ほかにも、寝る直前の食事はよくないので夕食の時間を少し早めるとか、カフェイン入りの飲料は昼間だけにするとか、夜のハードトレーニングや寝酒を避けるとか、できる範囲で試してみればよいと思います。まじめで高すぎる目標を掲げる人ほど、継続せず、睡眠も改善しない傾向があります。
地域や学校で話をする際は、そのような内容と合わせ、睡眠の仕組みも説明します。眠っている間には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の時間があり、「レム睡眠」の間は、体の休息・疲労回復と同時に、記憶の整理など脳のメンテナンスが行われます。一方、「ノンレム睡眠」の間は脳が休息し、体のメンテナンスが行われて成長ホルモンの分泌などが進みます。人間にとって、この両方の眠りを確保することが大切だ、ということを伝えます。子どもたちには分かりやすい言葉で説明し、「なぜ睡眠をとらなければならないか」を理解してもらうようにしています。
正しい知識を伝える「睡眠教育」の重要性
「睡眠教育」という言葉はまだ広く知られていないように思います。
古谷准教授:
もともとは「睡眠衛生」という言葉が使われていました。医療的な対応だけで睡眠の問題を改善しようとするのではなく、まずは科学的根拠に基づく正しい知識や、生活習慣を自分で調整する大切さを伝えていこうとする取り組みです。
近年、睡眠の悩みをテクノロジーで解決しようという「スリープテック」の活用が広まっており、睡眠の改善に役立つとされる機器や寝具、サプリメントなど、さまざまな商品も販売されています。しかし、それが科学的根拠に基づくものなのか、消費者には見極めが難しいと思います。実際の効果について私から良し悪しに言及することはできませんが、違和感があれば使用をやめるなど、個人の感覚を大切にしてほしいと思います。そういったことを伝えるためにも睡眠教育は重要だと考えています。

地域の講座などで話をすると、自分の睡眠に自信がない人が多いと感じます。自身の睡眠習慣について「大丈夫か」と質問されることが多いですね。睡眠は他人と比較することが難しいので不安になるのかもしれません。大切なのは、正解を求めすぎないことだと思います。自分自身と対話しながら、生活をコントロールし、睡眠の問題が起こらないように予防していくことが重要です。
私は医師ではないので、睡眠障害についての助言はしません。日中に過度な眠気が生じて生活に影響している場合などには、医療機関の受診も検討してみるよう勧めることはあります。最近は、睡眠外来を開設する医療機関が増えており、日本睡眠学会のホームページでも専門医の一覧を掲載しています。そのような情報は広く伝えていきたいと思います。
睡眠はウェルビーイングの基盤
最近は「ウェルビーイング」という概念が注目されていますが、睡眠との関係をどう考えますか。
古谷准教授:
睡眠は、食べることや動くことと同じく、より良く生きるための基盤だと考えています。この基盤がしっかりしていないと社会活動が困難になり、ウェルビーイングの実現にも影響します。また、睡眠は社会全体のウェルビーイングとも深く関係しています。睡眠の問題が重大な事故やヒューマンエラーにつながることもあります。一人一人の睡眠の状態が良くなければ、社会はうまく回っていかないということだと思います。
今後取り組みたい研究や活動は?
古谷准教授:
ストレスと睡眠の関係に関する研究を今後も続けていきたいと思います。ストレスによる不眠の予防策について、具体的な提案ができるようにしていきたいと考えています。医療に簡単にアクセスできない地域もあるので、睡眠問題の予防や、困った時の医療機関での相談の仕方などについて、分かりやすく情報提供できるようにしたいと考えています。
睡眠教育については、大阪府茨木市と連携し、来年度から中学校で継続的な取り組みを行う計画があります。日本睡眠学会に参加していた保健師の方から提案があり、準備を進めています。こうした実践を通し、どのような働きかけをすれば行動を変えるきっかけになるのか、といった課題を考えていきたいと思います。
古谷真樹准教授 略歴
2001年、ノートルダム清心女子大学人間生活学部卒業。2003年、同大学大学院人間生活学研究科修士課程修了。2006年、広島国際大学大学院総合人間科学研究科博士後期課程修了。博士(臨床心理学)。2013年、神戸大学大学院人間発達環境学研究科講師。2016年から准教授。