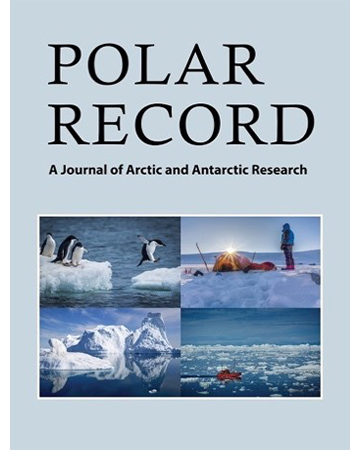先端科学技術を社会に導入する際、倫理や法的な課題にどう対応するか。その問題はELSI(Ethical, Legal and Social Issues=倫理的、法的、社会的課題。エルシー)と呼ばれ、国内外で研究が広がっている。神戸大学では2023年、全学横断の「神戸大学生命・自然科学ELSI研究プロジェクト(KOBELSI)」が発足した。医療やAI(人工知能)などの領域で次々に革新的技術が生まれる中、ELSI研究はどのように進んでいるのか。プロジェクトのリーダーを務める人文学研究科の茶谷直人教授(古代ギリシア哲学、生命倫理学)に、現状や課題、今後の展望を聞いた。
ヒトゲノム計画で注目された倫理的、法的、社会的課題
ELSI研究はいつごろから広がり始めたのでしょうか。
茶谷教授:
ELSI研究は20世紀末からアメリカで本格的に広がり始めたのですが、そこには二つの大きなきっかけがありました。
まず、1970年代ごろから分子生物学の分野が急速に発展し、遺伝子の仕組みの解明や遺伝子組み換え技術が進みました。それを治療に応用しようという動きも出始めました。一方で、その進歩によるリスク、例えばバイオハザード(生物学的危害)や技術の悪用などに対する懸念も、科学者自身から提起され始めました。そこで、DNAの二重らせん構造の発見で知られるジェームズ・ワトソン博士らが、いったん立ち止まって研究のあり方を考えるモラトリアム期間を設けようと提案したのです。それが1974年のことでした。
もう一つのきっかけは、1980年代からアメリカで動き始めたヒトゲノム計画です。これはヒトのすべての遺伝情報を解読しようという国際的な取り組みで、計画推進の過程でワトソン博士が「ELSI」の重要性を提唱しました。研究をする場合、予算のうちの一定割合をELSI研究に充てることを提案し、アメリカ政府もそれを受け入れて体制を構築していったという経緯があります。
遺伝子の解析が進むと、特定の遺伝子疾患の発症が予見される人が保険に加入できないとか、就職で差別を受けるとか、さまざまな不利益が生じる可能性があります。また、「人体の設計図」ともいわれる遺伝情報は、かつては想定されていなかった知的財産で、それを社会や法律がどう扱うかという点も課題です。ヒトゲノム計画の推進によって、こうした問題が急速にクローズアップされてきたのです。
アメリカ以外の国々での動きは?
茶谷教授:
ヨーロッパではナチス・ドイツが行った人体実験に対する反省があり、以前から、人を対象とする医学研究などで人権の問題を重視する傾向がありました。ヨーロッパでは「ELSI」ではなく、「ELSA」(Aはaspects=側面)という名称で研究が広がってきました。

一方、日本で本格的な取り組みが始まったのはここ数年です。内閣府が5年ごとに策定する科学技術基本計画の第5期(2016~2020年度)で、初めて「ELSI」の考え方が盛り込まれました。その後、公的な研究費助成でもELSIの分野が対象となり、ここ数年は国立大学などでELSI研究を行うセンターが設立され始めました。
神戸大学では2007年、人文学研究科の中に「倫理創成プロジェクト」が発足し、応用倫理に関わる研究・教育活動に取り組んでいました。兵庫県尼崎市の工業地域や東日本大震災でのアスベスト問題の調査、学術雑誌の発行、研究会などを行っており、その蓄積を生かす形で、2023年に全学組織の「生命・自然科学ELSI研究プロジェクト」がスタートしたのです。現在、文理の研究科を横断し、約20人の研究者が参画しています。
科学技術の開発段階から問題点を洗い出す
研究における倫理的課題は、ELSIという言葉が生まれる前からあったと思いますが。
茶谷教授:
近年は、科学技術の開発から社会実装までの期間が非常に短くなっています。しかも、いったん社会に導入されると、影響は広範囲で多様です。悪用への懸念があっても、既存の法律が追い付いていないという課題もあります。社会に広まってから問題点を考えていては遅いのです。
インターネットにしろ、スマートフォンにしろ、それがない社会にはもう戻ることができませんよね。急速に進化している生成AIもそうでしょう。生成AIは膨大なデータを取り込み、瞬時に答えを示してくれますが、欧米中心の世界で生み出される偏った表現、元のデータの著作権の問題など、さまざまな課題が指摘されています。
ELSI研究は、社会実装された後ではなく、科学技術の開発段階から課題を見極め、できるだけ解決しておこうとする点が特徴です。外部から問題を指摘するのではなく、新しい科学技術を開発している研究者と同じ輪の中に入って考えます。そのためには、倫理や法律などELSIの領域の研究者も、対象とする科学技術の専門知識をある程度理解しなければなりませんし、技術を開発している側も研究の社会的影響を考える必要があります。
ただ、同じ輪の中に入って考える場合、批判的精神が失われかねないという課題もあります。ELSIの視点を持つ研究者が入る枠組みができても、開発された技術を追認するだけになっては意味がありません。仕組みが整えば整うほど、そうした危険性を意識し、研究者同士のコミュニケーションを重視しなければなりません。
研究に欠かせない自律性、公開性
研究の軍事利用に対する考え方もELSIの重要なテーマですね。
茶谷教授:
「デュアルユース(両用)」という言葉がよく使われますが、その言葉には「軍事と民生の両用」「善用と悪用」という二つの意味が含まれます。
新しい科学技術には、デュアルユースの側面があります。私たちが普段利用しているインターネットも、カーナビなどに使われているGPSも、もとは軍事のために開発され、民生利用へと広がりました。反対に、民生利用の技術が軍事に転用される例もあります。
倫理学の分野で知られている二重結果説の「意図と予見」というキーワードをもとに考えたいと思います。新しい科学技術を社会の公益のため、民生利用の目的で開発しようとするのは「意図」です。しかし、その技術が犯罪や戦争に使われるかもしれないと「予見」されることもあります。予見される場合、その残虐性や侵略性、大量破壊兵器に使われる可能性など、さまざまな側面を考える必要があります。そして、本来の意図である民生利用の社会的利益がどれだけ大きく、どれだけ確実か、といった面を総合的に勘案し、「一定のデュアルユース性を許容できるか」を判断することになると思います。
日本は先の戦争で、大学の研究が軍事目的に利用された大きな反省があります。ですからこの問題は、ELSIの大きな論点です。極論を言えば、すべての科学技術は軍事利用につながる可能性がありますが、研究を進める際に最も重要なのは「自律性」と「公開性」です。自律性とは、研究が研究者の知的な関心から始まるものであり、外部から干渉されないということ。公開性とは、研究内容が論文などで公にされるということです。軍事目的であれば、基本的に研究は公開されませんよね。つまり、自律性と公開性を欠くことは学術研究の本来の姿に反します。
「バイオものづくり」の分野でELSI研究を推進
神戸大学生命・自然科学ELSI研究プロジェクトはどのような取り組みをしていますか。
茶谷教授:
神戸大学は2022年、「バイオものづくり」「医工学」「健康長寿」など5領域の研究拠点を核とする「デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク(DBLR)」という枠組みを構築し、産官学連携や社会実装をより強く意識した自然科学研究を進めています。そこでは、特にELSIの視点が必要になるということで、ELSI研究プロジェクトの発足につながった経緯があります。
今、私たちが特に連携しているのが「バイオものづくり」の分野です。生物由来の素材や微生物などを活用してさまざまな化学品や医薬品などを生み出す研究で、文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」にも採択されています。
バイオものづくりでは、遺伝子組み換えやゲノム編集といった技術を用いており、いかに社会の安心・安全を確保し、社会に受け入れてもらうかを考えなければなりません。社会に根付いた文化や伝統との整合性といった面も意識する必要があります。さらに、新しい技術による利益を特定の国・地域の人や富裕層だけが享受することを避け、不公平を生まない努力をしなければなりません。そのためにも、まずはそういった問題につながるような課題を見つけるところから始めます。
ELSIは幅広い分野の研究者が関与する領域であり、一部の研究者がすべての問題に対応できるわけではありません。プロジェクトでは、学内外の人々を招いて月1回程度の研究会を開いているほか、海外の大学とも連携しています。これまでに香港の嶺南大学、イタリアのジェノヴァ大学、スペインのバレンシア大学と交流協定を結び、今後、共同研究などを進めていこうとしています。

個人的に研究しているテーマは?
茶谷教授:
研究テーマの一つがインフォームド・コンセント(説明と同意)です。医療では、治療方針を医師に任せるのではなく、患者が説明を受け、理解したうえで自ら決定するというプロセスとして知られていると思います。人を対象とする医学研究でも、対象者に対する説明、同意、組織内での審査などを経て進めるというモデルができています。
こうしたプロセスは医療以外の分野でも必要だと考えています。生成AIであれ、遺伝子組み換えであれ、新たな技術の導入については、社会に説明し、理解や同意を得る過程が必要になるということです。
現在、特に研究しているのが、パーソナルデータ(個人情報)の収集、利用に関する問題です。私たちがネット上のサービスを利用する際、「同意」のボタンをクリックすることでパーソナルデータの提供に同意したことになる場合がほとんどだと思いますが、画面上に示された規約をきちんと読んでいる人はどれだけいるでしょうか。多くの人が「プライバシーが大切」と言いますが、実際の行動はそれに反しているわけです。これをプライバシー・パラドックスといいます。
一つのパーソナルデータでは個人を特定できなくても、さまざまなデータを組み合わせ、いわゆる「紐づけ」をすれば、個人の情報はかなり特定されてしまいます。人々がこうした問題を理解したうえでサービスを利用しているならまだいいのですが、知らない場合はきちんとした説明が必要です。私の研究では、パーソナルデータの管理の現状などを考察し、どうすれば実質的な意味での「同意」になりうるかを考えていこうとしています。その際、医療分野で進められてきたインフォームド・コンセントの成果を参考にしたいと思っています。
市民の「選ぶ権利」を重視すべき
今後のELSI研究が目指す方向性とは?
茶谷教授:
ELSI研究は、科学技術が社会にとって真の公益となり、人々を幸せにするのかということ、つまりウェルビーイング(身体的、精神的、社会的に満たされた状態)を追究するものといえます。ウェルビーイングは、私の研究分野である古代ギリシア哲学の「エウダイモニア(幸福な生)」という概念と共通しており、生きがいのある充実した生き方を表します。ですから、私たちの研究では、ELSIのE(Ethical=倫理的)を重要な基礎として考えています。
世の中の仕組みを変えるような科学技術を導入する場合には、すべての市民が当事者となります。その際、技術に関する説明を受けたうえで、市民が「選ぶ権利」を持つことが大変重要です。使う権利もあれば使わない権利もあるはずです。どうすればその手続きが可能になるのか、考えていきたいと思います。
研究者には、科学コミュニケーションの力が必要になります。社会実装をする前の段階で、市民との対話を重ね、議論の結果を研究に反映し、さらに市民にフィードバックするような仕組みが求められるでしょう。
最近は、ELSIとともにRRI(Responsible Research and Innovation=責任ある研究・イノベーション)という言葉もよく使われるようになりました。RRIは、研究者自身が研究段階でELSI的な課題を考えながら進めるという意味合いがより強いと思いますが、重要なのは言葉ではなく、考え方です。たとえELSIやRRIという言葉が廃れても、科学技術の進化が続く限り、向き合い続けるべきテーマだと思います。
茶谷直人教授 略歴
1995年、北海道大学卒。1998年、神戸大学大学院文学研究科修士課程修了。2001年、神戸大学大学院文化学研究科博士課程(文化構造専攻)修了、博士(学術)。日本学術振興会特別研究員、神戸大学大学院文化学研究科助手を経て、2007年4月、神戸大学大学院人文学研究科准教授、2019年10月から同研究科教授。2023年から神戸大学生命・自然科学ELSI研究プロジェクト(KOBELSI)のリーダーを務める。