
バブル経済崩壊後、1990年代から日本の賃金水準は低迷が続いている。欧米の先進国との差は広がり、シンガポール、韓国などにも追い抜かれてしまった。どうして世界の中で「日本一人負け」のような状況になっているのか。これから社会に出ていく大学生などの若者の働き方はどうなっていくのか。日本の労働市場、労働政策について研究している経済学研究科の勇上和史教授に聞いた。
賃上げが難しいエッセンシャルワークで人手不足
欧米やお隣の韓国などのアジア諸国では順調に賃金が伸びているのに、なぜ日本の賃金は低迷しているのでしょうか。
勇上教授:
玄田有史『人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか』(慶応義塾大学出版会、2017年)が参考になると思います。いろいろな分野の研究者が、様々な側面から問題にアプローチをしています。
経済学の教科書的な考え方では、人手不足(労働需要が供給を超過)になれば、賃金が上がるはずです。ところが、賃上げできるような産業が人手不足なのではなく、賃上げが難しい産業で人手不足になっているとすると、賃金が上昇しない可能性があります。実際に、医療、福祉、介護、保育などの分野で人手不足になっていて、これらの分野は公的なサービスに近く、介護報酬などの形でサービスの価格が決められています。このため、人手不足なのに賃金に反映できないと考えられます。これは労働力の需要側、労働者を雇う側の問題です。
もう一つは労働力の供給側、働く側の視点です。バブル経済崩壊後の「失われた30年」に、新たな働き手として労働市場に出てきたのは、高齢者と女性でした。公的年金の受給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられ、高齢者雇用安定法によって企業に65歳までの雇用が義務付けられました。働く意欲のある高齢者が、労働市場に残るようになりました。一方、女性は1970年代以降、労働参加率が伸びています。高齢者や女性は、終身雇用の正規労働者ではなく、非正規の形で働く人が多く、多少賃金が低くても働いてくれるのです。
賃上げしにくい産業で人手不足になり、賃金を上げなくても労働者が来てくれることから、強い賃上げ圧力が働きにくい経済構造、人口構造になっていると考えられるのです。
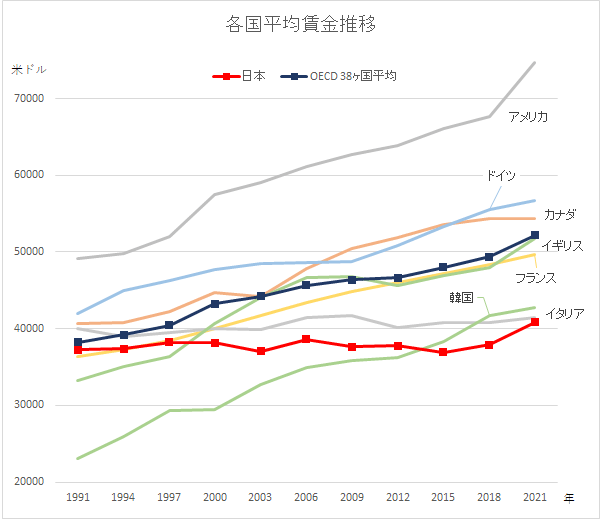
保育、医療、介護などのエッセンシャルワーカーが人手不足なのに賃金が上がらない、そんな状態がいつまでも続くものでしょうか。
勇上教授:
医療、介護、福祉、保育などでは、サービス価格を改定しても賃金には反映されない場合が多く、監督官庁が労働報酬を引き上げるよう指導することもあります。それぐらい賃金が上がりにくい職種にも関わらず、今のところはこれらのエッセンシャルワークに参入する人々(求職者)が一定数いらっしゃいますが、今後そのような人材が枯渇し、求職者が大きく減った時、いわゆる「転換点」を迎えるといわれています。
転換点の理論とは、発展途上国が工業化する過程で農村部から供給されていた低賃金労働者が得られなくなった時に一気に賃金が上昇することで、かつての日本の成長過程でも指摘されました。近年、介護現場などで人手不足になっているということは、低賃金でも働きたい人がいなくなりつつあることを示しています。人手不足分野では外国人労働者を受け入れようとしていますが、職場環境や労働条件の改善とセットで取り組まなければ、日本には来てくれなくなるでしょう。
正社員の賃金も低迷
正社員のホワイトカラー労働者の賃金も低迷していますね。
勇上教授:
バブル経済崩壊後、日本は右肩上がりの経済成長が望めなくなり、マイナス成長に陥った時期もありました。外国製品との競争、外資の日本市場参入、逆に日本企業が海外に生産拠点を移すなど、経済環境の変動が激しくなり、不確実性が増しています。
経済活動を心理学的な側面も踏まえて分析する行動経済学の視点で賃金を考えると、賃金は上がるとうれしく感じますが、下がるとやる気を失い、社員の生産性が下がってしまいます。労働者は特に名目賃金が下がることを嫌うので、業績が悪化しても賃金を下げることが難しい。企業業績の好不調に対応して賃金も上下させることができないのです。これを「賃金の下方硬直性」といいます。
高度経済成長の時代には賃金を引き上げても業績がさらに向上するという良いサイクルがありましたが、経済のマイナス成長を記録し、不確実性が高まった1990年代以降は、企業は業績が良くなっても賃金水準を引き上げるベースアップをせず、ボーナス、一時金で社員に還元しています。ですから、正社員全体の賃金水準が上昇しなくなったのです。
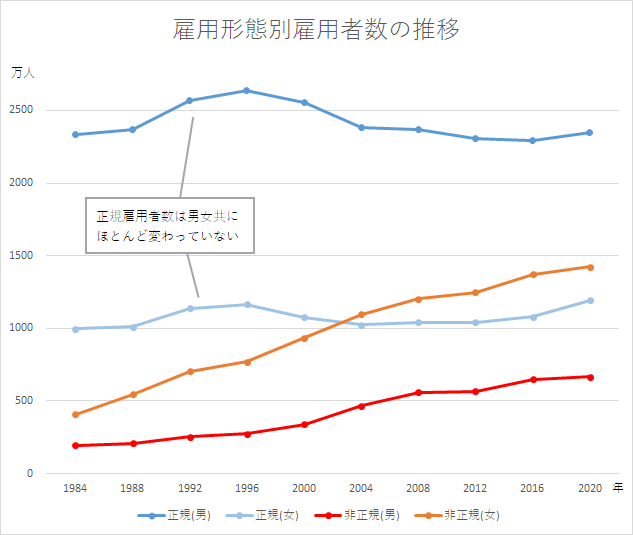
企業などが正社員の採用に消極的だった、いわゆる「就職氷河期」の影響も指摘されていますね。
勇上教授:
バブル経済崩壊後の30年で、正社員の数はほとんど変わっていません。ところが働く人の総数は増えており、増えた部分のほとんどが非正規の労働者です。好不況、業績の変動に対応する調整弁、のりしろとして非正規労働者の雇用を増減させて対応するようになったのです。正社員が年功賃金制度によって勤続年数と共に賃金が上昇するのに対し、非正規労働者は在職10年、20年でもほとんど賃金は伸びません。いわば常に新人扱いなのです。そのような非正規労働者が増えたことで、全体の平均賃金は下落しました。
一方、正社員に関しても90年代以降、企業は社員の訓練投資を減らしたことが観察されています。特に2008年のリーマンショック後は社員の研修費用が半減しました。1980年代まで、企業は株式の持ち合いによる安定株主と銀行融資に支えられていました。ところが1990年代の金融危機以降、銀行融資から株式発行などの直接金融中心になり、外資ファンドなどの株主が短期的な業績向上を求めるようになったため、成果が不確実でリターンに時間がかかる訓練投資が出来なくなったと思われます。正社員を訓練しスキルアップさせ賃金を引き上げるのが年功賃金の制度設計ですから、訓練投資の減少とともに正社員の賃金上昇カーブも緩やかになっています。
非正規雇用の増加、正社員の賃金上昇の鈍化の両面から、残念ながら日本全体の賃金水準が上がる展望は見えないのです。
変わるキャリア形成プロセス
これから社会に出ていく学生はキャリアをどのように形成していくことになるのでしょうか。
勇上教授:
他の国の若い人をみると、日本のように学卒後すぐに正社員になる国は稀です。若者は経験がない未熟練の労働者ですから、インターンシップや契約社員などの見習い期間で適性を見極め、経験を評価してもらって、それから無期雇用の定職に就きます。
日本でも新卒後すぐに就職する形だけでなく、留学して帰国後に就職を目指すとか、大学院に進むとか、若者のキャリア形成は一本の道ではなくなっていくと思います。
特定のポストに必要な技能を持っている人材を採用するジョブ型雇用が増えれば、大学で学んだことが直接キャリアにつながるようになるでしょうし、就職までのプロセスは多様化していくはずです。今後は企業でも大学院レベルの知識が必要になっていくと考えられるのに、大学院生が減っているのは世界で日本ぐらいです。
ただ新卒で正社員として雇用し、訓練してもらえるなら、その機会は利用したらいい。自分の適性を見つけ、その会社で自分の目標を達成できるなら、そこで働き続け、そうでなければ転職する。ただ、どんなに自分に合った会社でも合併や倒産することもあるから、自分のスキルが他の会社でも通用するかを常に考える「外の目」を持っておくことが大切でしょう。
これからは70歳まで働くことになるのだから、仕事の中身はどんどん変わっていきます。公的支援を受けて再訓練の機会を得るとか、奨学金を得て大学院に入り直すとか、自分の能力をアップデートしていく努力が求められるのではないでしょうか。
最近、一部の業績優良企業の高賃金や高初任給が話題になっていますが、このような賃金格差は今後も拡大していくのでしょうか。
勇上教授:
企業での入社後の経験より、大学・大学院で学んだ知識が最先端スキルの証明になるとして、ITエンジニアなど特定の職種の人材を高い処遇で確保する動きが確かにあります。しかし、最近の研究では、長期的に企業内で人材育成する日本の雇用システム全体を揺るがすような現象にはなっていないとみられています。
企業は賃金表、賃金ルールを持っていますが、自前では育成できない高スキルの人材はその賃金ルールとは別に扱います。既に企業内で働いている人は、そのような助っ人を「別の人だ」と認識しますし、助っ人は大量ではありません。新卒採用から時間をかけて幹部を養成していく日本型の雇用慣行はいまのところ維持されていると思われます。
格差拡大に歯止めを
AI(人工知能)技術などの進歩によって、人間の仕事がなくなっていくという見方もあり、いっそうの格差拡大が懸念されています。ベーシックインカムなどの政策が世界で論議されていますが、どのように考えますか。
勇上教授:
格差が拡大することがなぜいけないのか。これは格差が、個人の能力だけでなく、運や偶然の要素にも左右されるにも関わらず、一度生じた格差は、機会の不平等を通じて固定化するためです。さらに、格差が大きいと、恵まれた他人と比較して嫉妬、羨望の気持ちを持つ人が増え、社会が不安定化することが懸念されます。中間層が分厚く存在する社会では、極端な考え方、判断をする人が減り、政治・経済をうまく動かしていくことができると考えられます。
ところが、日本では生活保護受給者が増えています。現役世代の受給者は景気変動によって増えたり減ったりしていますが、高齢者の受給者が増え続けています。(税、社会保障などでの)再分配後の格差はそんなに広がっていないデータがありますが、相対的貧困率(所得中央値の半分以下の所得しか得ていない人の割合)が下がっていないのが問題です。
これに対し日本では、生活保護制度によって、憲法25条が保障している健康で文化的な最低限度の生活を支えようとしていますが、世界各国では、働ける(が収入の低い)層には「負の所得税」や「給付付き税額控除」という別の政策が議論されています。
これは働いているが収入の低い人たちに対し、収入の一定の割合の「税金」を給付する、というものです。所得から一定割合を徴収する普通の税金を「ポジティブな所得税」とすると、給付するのは「ネガティブな所得税、負の所得税」です。たとえば年収100万円の人に20%に相当する20万円を給付するというような形です。
生活保護制度では受給者が働いて得た収入の分だけ保護費が減らされ、就業しても合計の収入は増えません。「給付付き税額控除」では働いた収入に一定割合をプラスして給付するので、就業のインセンティブを損なわないのです。お隣の韓国や英国、米国でも行われており、かなり多くの国が導入している政策です。日本でも導入が議論されたことはありますが、個人の年収を正確に把握する納税者番号などの制度が無いことを理由に、見送られてきました。
この問題に対して、「ベーシックインカム」は、子どもから大人まで、個人に一定額を給付することで社会保障制度を簡素化する点にポイントがあると考えられます。既存の所得再分配や社会保障を置き換えようという考え方であって、必ずしも格差縮小を目指した政策ではないと思います。ベーシックインカムも負の所得税も追加の税財源が必要だとされていますが、そうした財源問題や、他の社会保障とどのように組み合わせるのかなど、具体的な議論は進んでいないのが現状だと思います。








