長寿化、少子・高齢化は社会にどのような影響を与えるのか。産業構造はどのように変化し、政策対応には何が求められるのか。日本と世界が直面する課題の解明に、マクロ経済学の手法で挑戦している衣笠智子教授は、「世代重複モデル」などの分析手法とデータに基づいた実証研究で、人口減少下の農業振興などについて政策提言につながる研究活動を続けている。

世代重複モデルとはどのようなものですか。
衣笠教授:
異なる世代が存在することを考慮したマクロ経済学のモデルです。労働者が生産の主体なので、かつての経済学では全員が労働者と仮定するモデルでした。世代重複モデルは、労働者だけでなく、若年層や高齢者など働いていない世代=異なる世代の存在を考慮するモデルです。サミュエルソンなど著名な経済学者によって、1960年代半ばから消費や貯蓄について分析する理論として使われるようになり、現在では人口変化、年齢構成の変化、長寿化が経済行動に与える影響の分析に活用されています。
長寿化の貯蓄に対する影響を分析されたそうですね。
衣笠教授:
消費は所得と連動すると考えられていましたが、実際には所得の上昇ほどには消費が増加しません。その理由として、世代重複モデルでは (個人が) 生涯の所得を考えた上で消費と貯蓄に配分していると考えるのです。すべてを消費するのではなく、収入がなくなる老後に備えて、貯蓄に回すと考えられます (ライフサイクル仮説)。寿命が伸びると、老後に備えるために貯蓄率が上昇すると予想され、私は、世銀などのデータを使って計量的にも分析しました。
欧米、オーストラリア、日本、韓国などでは長寿命化に伴って貯蓄増加が確認できました。一方、アジアやラテンアメリカの発展途上国のデータでは貯蓄増加は認められません。これは高齢期になったら子どもに面倒を見てもらうという家族内のサポートのシステムが関係していると思われます。
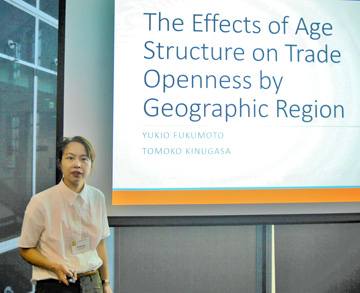
長寿化に伴って貯蓄が増えると、経済、社会にどのような影響を与えるのでしょうか。
衣笠教授:
日本では第2次世界大戦後、特に高度経済成長期に急速に貯蓄が増加しました。個人の貯蓄は金融機能を通じて産業に投融資され、経済成長にはプラスの相関があります。現在は平均寿命の伸びが緩やかになり、貯蓄の伸びも緩やかになっています。
現役世代は長寿化に備えて貯蓄を増やしますが、一方で貯蓄を取り崩して生活する高齢者もいます。ですから、寿命の伸びのスピードも貯蓄率の上昇に大きな影響を与えることを、欧米、日本、韓国などの先進国のデータで、明らかにしました。
世代重複モデルは、他の分野の研究にもいかせるのですか。
衣笠教授:
最近は「人口と貿易」に関する研究にも取り組んでいます。年齢構成の変化が貿易に与える影響を、貿易開放度とよばれる指標で考えます。この指標は、輸出額+輸入額/GDP (国内総生産) で算出するもので、その国がどれくらい貿易に依存しているかを見るものです。子どもや高齢者が多いと貿易開放度は下がると予想されます。子どもや高齢者は、教育や医療・介護など貿易しにくいものをより多く消費するからです。逆に生産年齢人口が多い国の貿易開放度は高くなります。
私は世界の貿易、人口構成のデータを分析して、上記のような傾向を確認しました。戦後の日本のグローバリゼーションの進展は、GATT、WTOなどの自由貿易の国際的な制度だけでなく、人口構成の変化も関係しているということを、学問的に明らかにしました。
先進国では長寿化の一方で出生率が低下し、日本では人口減少も始まりました。
衣笠教授:
発展途上の段階では子どもの死亡率が高いので、それを補うためにたくさん産む多産多死の状態ですが、医療が発達し栄養状態が向上して死亡率が下がると出生率が下がる「人口転換」が起こります。先進国になると労働力としての子どもの重要性は下がり、社会保障が充実すると老後の面倒を見てもらうために子どもを育てる必要もなくなります。一方、教育費など子育ての費用も高くなり、女性の社会進出によっても出生率は下がります。
わが国の少子高齢化は年金制度などに負の影響があると考えられるので、出生率を上げる努力は重要です。しかし、出生率を劇的に上げることは難しいので、少子高齢化の影響を緩和することを考えることが必要です。女性や高齢者に働いてもらうこと、少なくなる労働のクオリティを上げるためにしっかり教育することなどです。
また、長寿化の良い部分を活かすことを提言しています。寿命が伸びて増えた貯蓄が投資され、将来の成長につながります。高齢になっても貯蓄できるように、高齢者がしっかり教育を受けることが重要です。

人口減少時代に農業の重要性が高まるそうですね。
衣笠教授:
人口が減って貯蓄が減ると、全体の資本も減少します。それは農業、非農業のどちらにもマイナスですが、マクロモデルをつくって分析すると、非農業のマイナス幅の方が大きい。例えば、所得が減っても農産物の需要は所得弾力性が低い、つまり必需品なので需要が減りにくいなど、相対的に農業の重要性が高まると予想されます。
また、最近では保水機能などの環境保全、景観など農業の社会的意義も注目されるようになっていますし、山間地など非農業には適さない場所でも農業なら行うことができるため、人口の一極集中を緩和する機能も期待されます。不況期には農業が雇用の受け皿になってきたことも時系列データで確認されています。もちろん、農業を成長産業にしていくためには、農業に安定して取り組める政策が必要なことは言うまでもありません。
農業を振興するためには何が必要なのでしょうか。
衣笠教授:
農業の成長要因を計量的に分析していますが、
- 公的研究機関のデータで確認できる農業分野の研究開発投資額
- 一農家当たりの経営規模
- 農業依存度 (農家所得に占める農業所得の割合)
——などが大きいほど、生産性が高まることが確認できます。よく言われていることですが、専業化を進め、経営規模を拡大することが重要なのです。そのために規制緩和を進め、「家」中心の小さな経営主体から株式会社など法人の農業経営を認めることや、農業生産 (第一次産業) に加えて、農産物加工 (第二次産業) 、流通・販売 (第三次産業) まで農業者が手がける「六次産業化」などを通じて高付加価値の産業に変えていくことが課題になりますが、学問的データに基づいた政策提言に取り組んでいます。
大阪府能勢町と協力して2012年に農家の意識調査を行いました。全体の約8割が農業経営の現状維持を見込んでいましたが、土地の貸し付けや農作業委託を希望する意見が約2割あり、高齢化の進展によって5~10年後には農地の流動化・集約化の受け皿となる農地利用集積化円滑化団体 (行政が関与する農業公社のような組織) が必要になることを提言しました。中山間地農業の規制改革で国家戦略特区の指定を受けた兵庫県養父市から研究対象にするよう提案されており、今後、企業の農業参入や人材確保に関する調査を考えています。
最後に女性研究者が活躍する条件についてうかがいます。日本の大学・研究機関はまだまだ女性研究者が少なく、もっとダイバーシティ (多様性) を高めることが課題になっています。ご自身の経験からどのようにお考えですか。
衣笠教授:
確かに結婚・出産によって研究活動を中断する期間があると、男性に比べて不利になることは否定できないと思います。私は地元 (兵庫県) 出身で親のサポートを受けられましたし、配偶者も研究者ですので、現在小学生の子ども2人の子育てと研究の両立については恵まれた環境でした。しかし、保育所の充実などの条件整備は絶対必要です。特に任期付きポストにいる30歳代の女性研究者は、出産・子育てと研究を両立できるのか、心配していると思います。学内の行政的業務や教育負担を軽減するなど、女性研究者を支援することを考えなければならないと思います。
略歴
| 1998年 | 神戸大学経済学部 卒業 |
| 2000年 | 神戸大学大学院経済学研究科博士課程前期課程 修了 |
| 2004年 | University of Hawaii Ph.D. in Economics 修了 |
| 2000年6月~2004年8月 | 神戸大学経済学研究科 助手 |
| 2004年9月~2006年3月 | 神戸大学経済学研究科 講師 |
| 2006年4月~2016年3月 | 神戸大学経済学研究科准 (助) 教授 |
| 2016年4月~現在 | 神戸大学経済学研究科 教授 |
| 2017年4月~現在 | 神戸大学社会システムイノベーションセンター 副センター長 |








