兵庫県立美術館で開催されている特別展「リビング・モダニティ 住まいの実験1920s―1970s」を鑑賞、テーマ別に参加者が話し合う演習・ワークショップ(神戸大学主催)が9月26日に行われました。本学・文学部、人文学研究科と工学部、工学研究科の学生21人が参加し、展覧会鑑賞とワークショップを通じて、半世紀にわたる住まいの実験への理解を深めました。本学地域連携推進本部が、同美術館の協力を得て、演習・ワークショップの企画を支援しました。
ル・コルビュジエ(スイス出身、フランスで活躍)やルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ(ドイツ出身)ら多くの建築家が1920年代以降、時代とともに普及した新たな技術を用いて、機能的で快適な住まいを探究しました。その実験的なビジョンと革新的なアイデアは、やがて日常へと波及し、人々の暮らしを変えることになります。
本展覧会は、当代の暮らしを根本から問い直し、快適性や機能性、芸術性の向上を目指した建築家たちが設計した戸建てのカギとなる14邸の住宅を年代別に紹介しています。20世紀に始まった住宅をめぐる革新的な試みを、衛生、素材、窓、キッチン、調度、メディア、ランドスケープというモダン・ハウスを特徴づける7つの視点から再考しています。
本学の演習・ワークショップは、県立美術館の担当学芸員が展覧会の見どころを説明するレクチャーで始まりました。同展は、3月から6月まで東京・国立新美術館で開催されましたが、同館との展示の違いや、ル・コルビュジエの代表作「ヴィラ・ル・ラク」の実物大の水平連続窓を再現した際の舞台裏を披露してくださいました。続いて、大学院人文学研究科の長坂一郎教授が「実験としてのデザイン―仮説・検証の先へ」をテーマに、大学院工学研究科の高田暁教授が「藤井厚二の実験住宅と健康・快適な住まい」と題して、各30分間、イントロダクションを行いました。長坂教授は、住宅デザインの転換期となった半世紀を紐解き、「実験の手続き」という手法に沿って、各建築家の作品を背景、目的、方法、実験、結果、展望の各面から分析し紹介しました。高田教授は、大正時代から昭和時代初期に活躍した建築家・建築学者・藤井厚二の人生に触れながら、生涯5度も建てた実験住宅、代表作の「聴竹居」(ちょうちくきょ)について解説しました。その後、参加者は1時間程度、展覧会を鑑賞しました。
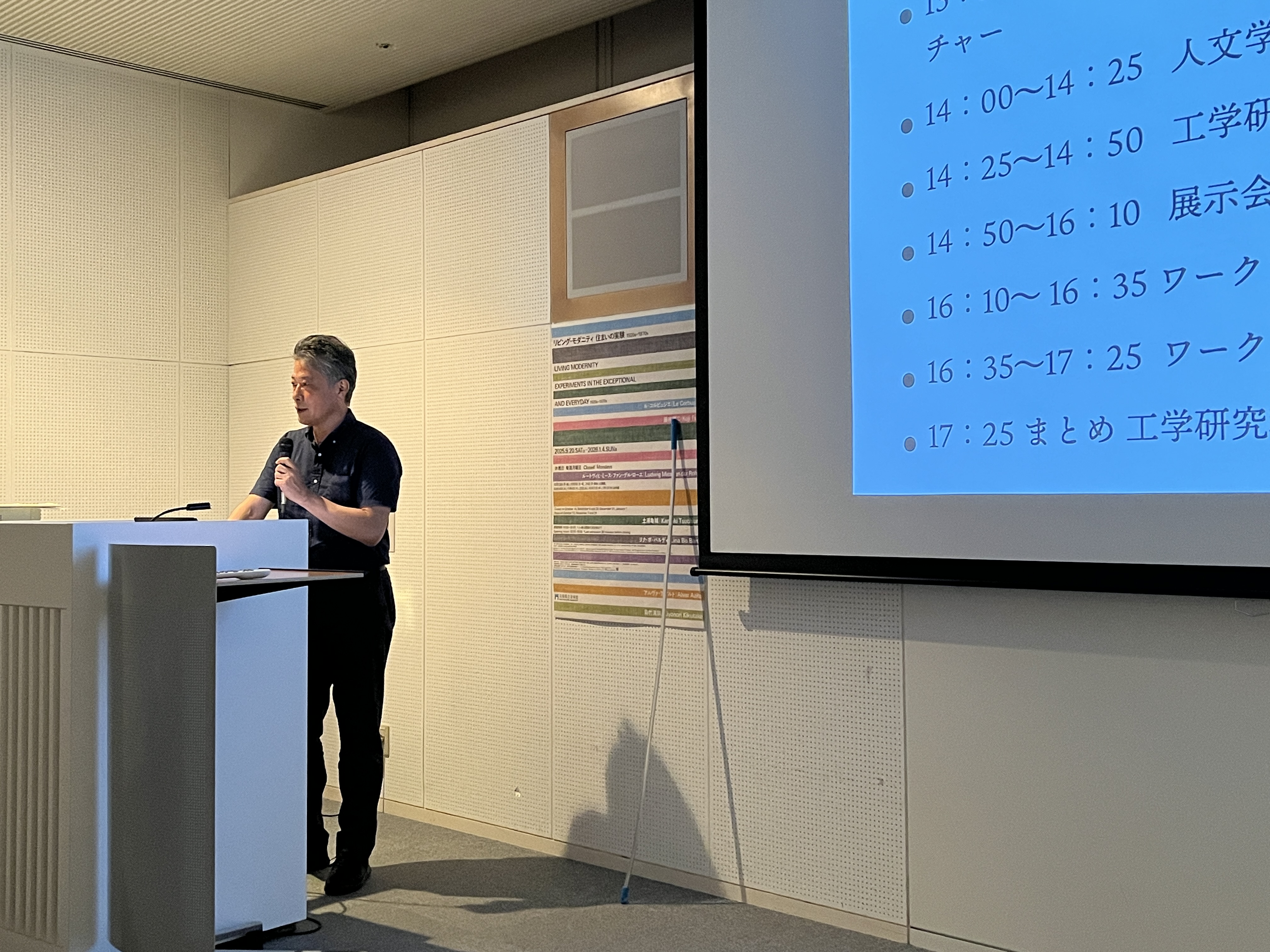
「実験としてのデザイン」をテーマに話す長坂一郎教授

藤井厚二の実験住宅について解説する高田暁教授

続いて、「『住まいの実験』を通して21世紀の『住む』を考える」をテーマに、振り返りワークショップをしました。今回の展覧会では、衛生、素材、窓、キッチン、調度、メディア、ランドスケープの7つの視点で、各建物を再考していましたが、参加者は3~5人でグループを組み、「『現代』に求められる『ストラテジー』(必要な視点)とは何か」について活発な意見交換をし、発表をしました。
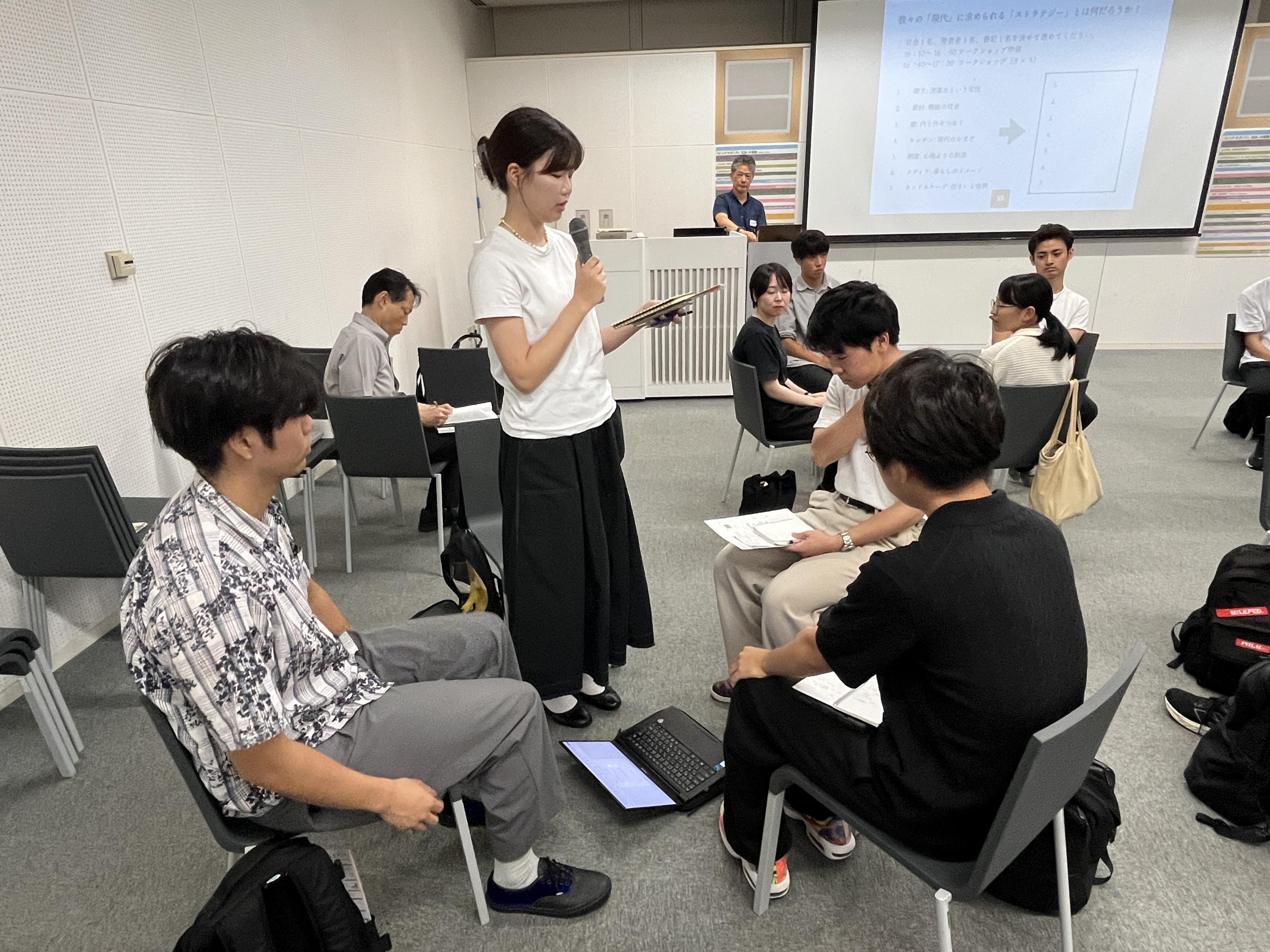
展覧会鑑賞を終え、振り返りワークショップをする参加者

兵庫県立美術館でのワークショップを総括する鈴木広隆教授
最後に、工学研究科の鈴木広隆教授が演習・ワークショップ全体を振り返りながら、「ワークショップを通して多くの気づきがあったのでないでしょうか。話し合うのは短い時間だったと思いますが、その時間の中で一定の成果を出せたことはよかったと思います。今回の経験を今後に生かしてください」と総括しました。
関連リンク
特別展「リビング・モダニティ 住まいの実験1920s―1970s」(兵庫県立美術館HP)
(地域連携推進本部、連携推進課)
