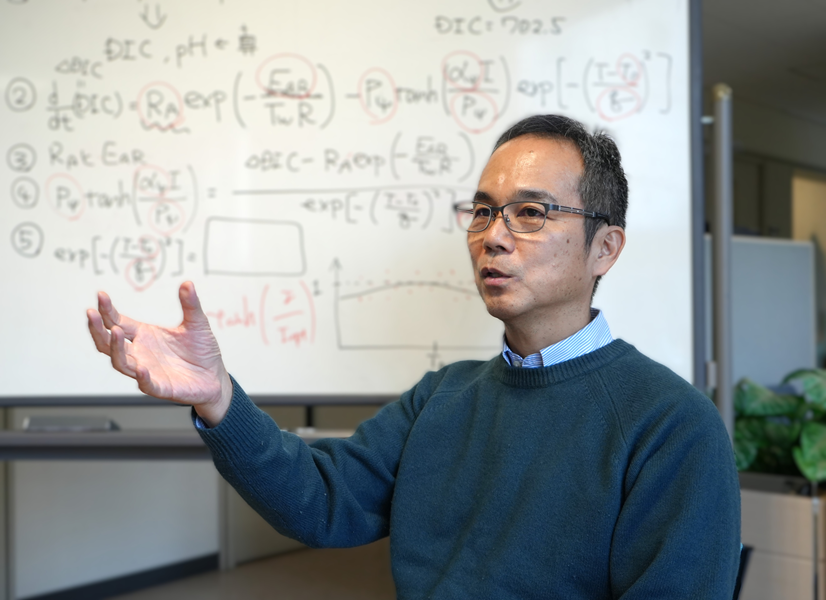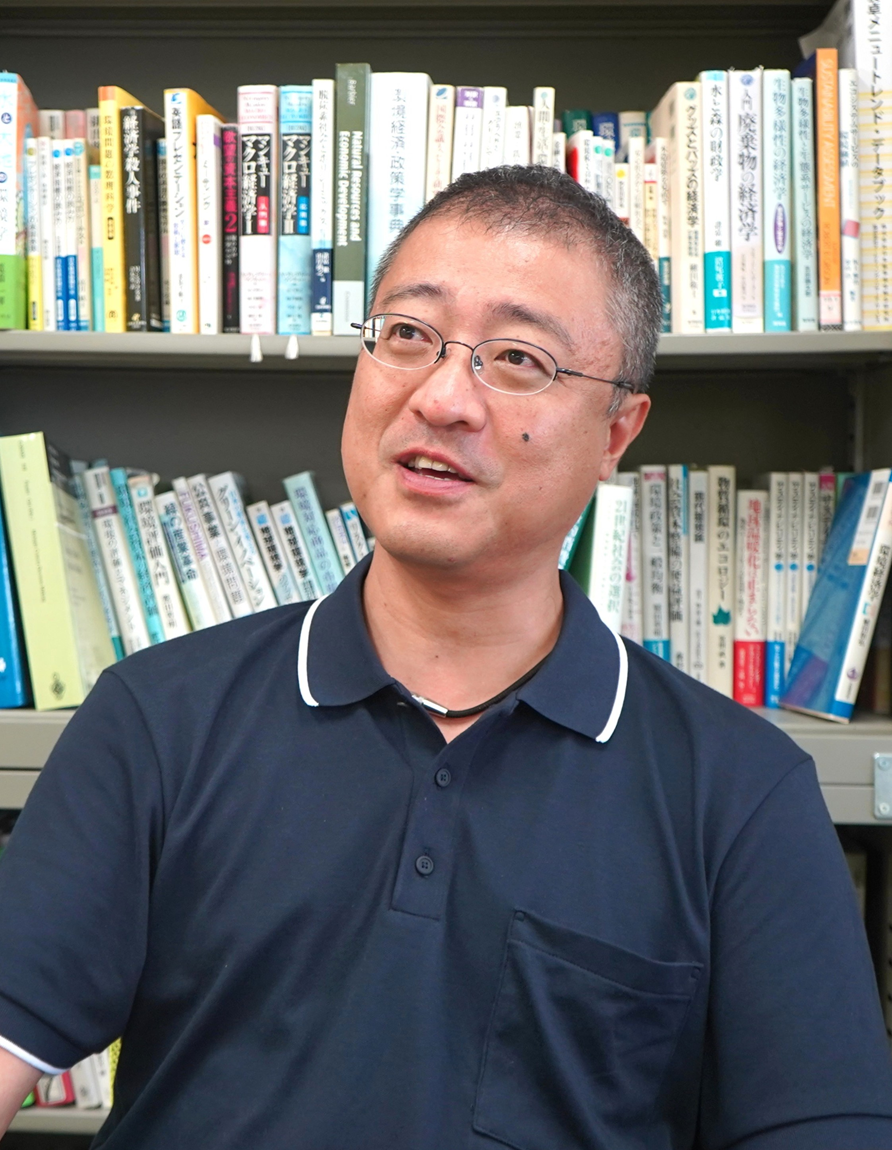
経済と地球環境の問題は切り離して考えられない。人間の経済活動によって地球温暖化は加速度的に進み、生物多様性の保全も危機に直面している。その現状を経済学の観点から分析し、解決策を見出そうとしているのが、人間発達環境学研究科の佐藤真行教授(環境経済学)だ。深刻化する地球環境問題に対し、どのようなアプローチが考えられるのか。研究の現状や展望を聞いた。
環境経済学の研究は異分野融合
環境経済学とはどのような研究分野ですか。
佐藤教授:
今、人間の経済活動の肥大化によって、廃棄物やエネルギーといった身近な生活に関わる問題から地球温暖化や生態系破壊のようなグローバルな問題まで、環境に関する多面的な課題が深刻化しています。その要因やメカニズムを分析し、問題を最小限にする社会経済システムを考えるのが環境経済学です。
イギリスの経済学者アーサー・ピグー(1877~1959)の提唱をもとにして「環境税」や「炭素税」のようなアイデアの萌芽は古くからありましたが、一般の人々が経済と環境問題のつながりに関心を持ち、現実的な議論が加速したのは、1997年に京都市で開かれた「国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)」のころからではないでしょうか。この会議では、温室効果ガスの削減目標だけでなく、排出枠を国同士で売ったり買ったりして削減目標を達成する「削減方法」が合わせて提起されました。
COP3は地球温暖化対策の節目となりましたが、地球環境問題のもう一つの大きなテーマ「生物多様性の保全」で重要な節目となったのは、2010年に名古屋市で開かれた「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)」でしょう。私たちを取り巻く生態系にはどのような価値があり、保全にどれだけのコストがかかるのか、といった経済的価値に関する議論も盛んになりました。
経済学の役割の一つとして、生態系の価値、保全のコストを評価して定量化し、「可視化」することがあります。そのうえで、価値を守るための政策、制度を構築して実行に移す「主流化」(メインストリーミング)を進める必要があります。例えば、近年、企業が自社の活動による生態系への負荷や保全対策について情報開示をする動きが広がっていますが、こうした取り組みを推進する制度設計も環境経済学が担う分野です。
そのような「可視化」「主流化」は、どのように進めていくのでしょうか。
佐藤教授:
まずは工学、農学、生態学など自然科学分野の研究者と連携し、大気汚染や森林、生物の状況、都市計画の動きなどを把握することが必要です。また、政策や制度を構築する「主流化」では、法学や政治学分野の研究者との連携が欠かせません。さらに、人々が環境にどのような価値を感じるのかといった面では、心理学や、時には健康科学的なアプローチも大切です。環境経済学の研究は学際的で、異分野融合で進める必要があります。
政策提言については、環境省、内閣府など省庁との連携で行っています。環境省は「環境研究総合推進費」という研究費を設けており、その制度による研究プロジェクトには、私も含め全国の多数の研究者が関わっています。
我が国は、2022年のCOP15で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」をもとに、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として保全する目標「30 by 30(サーティ・バイ・サーティ)」を掲げています。そして、目標達成に向け、生物多様性の保全に資する地域(OECM=Other Effective area-based Conservation Measures)の登録を推進しています。私は、この地域の登録について、企業や民間組織からの申請を増やすための経済的インセンティブをどのように導入するかという制度設計に関わっています。
このOECMについては、神戸市北区山田町の一部も、2024年に日本で初めて登録された地域の一つに含まれていて、私の研究グループでも神戸市と連携して調査や分析を進めています。
人口の偏在は里山の劣化と結び付いている
最近は特に、都市や都市近郊の生態系に注目して研究しているそうですね。
佐藤教授:
人間社会の身近にある里山に注目し、現代のライフスタイルの変化を踏まえた生態系の機能や有効な保全方法について研究しています。里山の生態系は、近隣の都市に暮らす人々にさまざまなメリットをもたらしています。例えば、災害の防止、水質の保全、ヒートアイランド現象の緩和などです。人々が自然に触れて楽しむ場としても重要です。ですから、私たちは都市化による便利さ、経済効率だけでなく、里山を保全するメリットにも目を向ける必要があります。それによって、生活の質(QOL=Quality of Life)を高めることにもつながるはずです。
一方で、都市に人が集まるということは、地方に人がいなくなることでもあります。下草刈りや枝打ちなどの手入れをすることで環境が保たれていた里山が、人の不在によって劣化していっています。日本の自然のほとんどは人の手が入ることで保たれてきた面があるので、地方の人口減少は環境保全の問題と深く結び付いているのです。このような観点からも、均衡ある発展のあり方を検討していかなければなりません。
自然環境の価値を測るのは難しそうです。
佐藤教授:
自然環境の価値を測る「ものさし」を作るのは、現在の研究の大きなテーマです。近年、世界でも日本でも「自然資本評価」というキーワードで多くの研究が進んでいますが、もっと人々のライフスタイルや生活の実情に根差した評価ができないか、と考えています。身近な自然に価値を感じるかどうかは人によって異なりますし、自然を利用できる環境にいるか、といった違いもあるからです。
最近、「体験格差」の問題がよく指摘されますよね。自然を利用するには、自由に使える時間や移動手段が必要で、所得格差との関連が懸念されることもあります。自然の中で虫や魚を捕まえたり、美しい星空を見たりする体験を通し、自然の価値の受益者となる層は偏っているということです。また、幼少期に自然体験が豊富な人は、自然を楽しんだり守ろうとしたりするマインドが生まれやすいとされています。一方、都市部であまり自然に触れずに育った人は、自然を守ろうという意識を持ちにくいとの指摘もあります。ですから、子どもたちへの環境教育、自然教育の機会は重要といえます。
これまでの多くの研究では、平均的な人を想定し、自然の価値を評価していましたが、細かい分析をする場合は、車を所有しているか、子どもがいるか、といった一人一人の社会的条件を踏まえた「ものさし」が必要になります。そうした評価のものさしを作ったうえで、格差をなくすための政策や制度設計も提案していきたいと考えています。
導入された森林環境税。使い道の指針が必要
政策や制度を構築する難しさもあるのでは?
佐藤教授:
環境を守るための財源は限られているので、何を保全するかを選択していかねばなりません。生態系保全についていえば、危機的な状況にある生態系から検討するとか、自然にアクセスしにくい人の課題を優先して考える、といった対応が必要でしょう。
日本では、2024年度から森林環境税(国税、1人あたり年額1000円)が導入されました。しかし、まだ使い道を模索している自治体もあり、なんらかの指針が必要です。財源の調達と使い方はセットで考え、より効果的な制度にしていかなければなりません。
企業に対しても、負担を求めるだけでなく、自主的な環境対策を促す仕組みづくりが大切です。企業は、社会から評価を受ければ、対策に前向きになります。
2015年、企業の気候変動対策の開示を推奨するTCFD(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures=気候関連財務情報開示タスクフォース)という国際的組織がスタートしました。2021年には、企業の経済活動による自然環境や生物多様性への影響を評価し、情報開示するTNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures=自然関連財務情報開示タスクフォース)という枠組みもでき、さまざまな企業が情報開示に取り組み始めています。
一人一人が、都市のあり方を真剣に考えなければなりませんね。
佐藤教授:
都市のグリーンスペース、ブルースペース(陸上の水域や水路で構成される領域)を保全する大切さについては、少しずつ理解が広まっていると思います。たとえば大阪・梅田の中心部の再開発では、緑地や水域を意図的に配置した「グラングリーン大阪」というエリアが誕生しています。都市デザインにおいて生態系の機能が評価されたものであり、私たちの研究グループも注目しています。
生態系を保全するまちづくりが人間にとっても良いと分かれば、保全の意識がさらに広がり、人間の活動と自然環境が調和する「環境共生」につながると思います。
自然の価値を可視化しなければ、いつの間にか失うことも
世界と日本の研究の比較から見えてくることはありますか。
佐藤教授:
東京圏ほど巨大な都市域は世界的にも珍しいでしょう。また、日本全体としては急激な人口減少に直面しており、日本はこれらの「課題先進国」と言われています。こうした状況を研究し、同じような課題が出てきそうな国々に発信できる成果が見えてくれば面白いと思います。
また、日本は災害が多いので、自然環境や生態系を活用して災害リスクを軽減する「エコDRR」(Ecosystem-based Disaster Risk Reduction)についてもかなり議論されてきました。東日本大震災の復旧・復興では、巨大災害への対応としてコンクリートの防潮堤が建設されましたが、一定規模の災害の対策としては海岸沿いの林や河畔林なども役立ちます。都市の緑地を保全する政策と両立することも可能でしょう。自然資本が人工資本をどう代替できるかという課題は、今後も検討していくべきテーマだと思います。

一方で、世界でも都市域における生態系の機能や保全についての研究は盛んで、日本が海外に学ぶ部分もあります。たとえば欧州の都市における木影の価値の研究があります。欧州でも夏季における都市域の高温が懸念されていますが、街の中に木があることで、暑さが緩和され、住民が自然の価値として感じていると指摘されています。
日本でも熱中症の予防策などとして、その価値がとても大きいと評価されれば、緑地や木の保全をもっと進めよう、ということになるでしょう。このように、自然環境の価値というものは、時代や使う人によって変わっていきます。
環境経済学は、人間のウェルビーイング(身体的、精神的、社会的に良好な状態)にどう貢献するでしょうか。
佐藤教授:
ウェルビーイングとの関係でいえば、すでに2000年代初め、国連の「ミレニアム生態系評価」で、ウェルビーイングに及ぼす影響の観点から生態系の機能が評価されていました。ケンブリッジ大学の経済学者、パーサ・ダスグプタ教授も、2001年に「Human Well-Being and the Natural Environment」(人間のウェルビーイングと自然環境)という本を出版しており、私も大変影響を受けて、在外研究で同大学に滞在しました。
人間の健康にとって森や海の恵みがどれだけ重要か、といった分析はさまざまな研究で行われてきました。自然が人間の生活の基盤となり、生活の質を高めることは確かです。ただ、それがどの程度かを示すのが難しく、定量化や可視化を目指す私自身の研究につながっています。
ウェルビーイングという言葉が示す意味は幅広いのですが、その重要な点は「幅広い選択肢があること」です。森と海のどちらに行くかを選択できる環境は、たとえ森にしか行かないとしても、森しか選択肢がない状況より豊かだといえます。つまり、行動の結果だけを評価するのではなく、行動できる幅の豊かさがウェルビーイングにつながるということです。
神戸のようにすぐ近くに豊かな自然がある都市は、それが強みといえます。しかし、その価値を意識的に見つめ、可視化をしないと、いつの間にか失うという状況にもなりかねません。そういう意味で、自然環境や生態系の価値の可視化は、今後ますます重要になると考えています。
佐藤真行教授 略歴
2001年、京都大学経済学部卒。2006年、京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学)。日本学術振興会特別研究員、京都大学地球環境学堂助教、京都大学フィールド科学教育研究センター特定准教授などを経て、2012年、神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教授。2019年3月~2020年3月、ケンブリッジ大学客員研究員。2020年、神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授。2022年から神戸大学ウェルビーイング先端研究センター環境領域研究部門長を兼務。